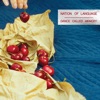NYブルックリンを拠点とするシンセポップ・トリオ Nation of Language、ニューアルバム『Dance Called Memory』を Sub Pop から 9/19 リリース!ニューシングル「In Your Head」を公開しました。シンセポップ、ミニマル・ウェーブ、ポストパンク、ゴス、ニュー・ロマンティック──ファンも評論家も、Nation of Language の魅力的な音楽を表現するために、古びたジャンル辞典を総動員してきました。
そして、もしこのバンドをうまく定義できないのだとしたら、それこそが彼らの本質なのです。フロントマンのイアン・リチャード・デヴァニーは、シンセサイザー主導の音楽が呼び起こせる感情の幅を次々と広げており、その作品は感覚を超えた旅であると同時に、あまりにも人間的な終着点でもあります。そうした体験をもとに、彼はバンドの4作目となるアルバム『Dance Called Memory』を書き上げました。幽玄で広がりのあるこの作品は、彼がただギターをつま弾きながら、メランコリー(憂鬱)に少しずつ向き合うという、ごく慎ましいやり方で生まれたものです。「落ち込んでいるときに自分を紛らわすには、最高の方法なんだ」と彼は語っています。
先行シングル「Inept Apollo」のMV公開!
Nation of Language の最初の2枚のアルバム『Introduction, Presence』(2020年)と『A Way Forward』(2021年)は、パンデミック中に登場した救いのような作品であり、私たちの集団的な閉塞感を美しく、共感できるサウンドで包み込んでくれました。しかし、彼らを単なるカルチャーの異端児から批評界の寵児へと押し上げたのは、2023年の『Strange Disciple』。このアルバムは Rough Trade の「年間最優秀アルバム」にも選出され、Pitchfork は「彼らは “大きく、そしてより良くなる” ということを学びつつある」と評しました。
デヴァニーの使命は、個人の絶望を、他者と共有できる慰めの形へと翻訳することにあります。その精神はアルバム全体に不思議なほど染み渡っており、シングル「Now That You’re Gone」では、その象徴ともいえる深い哀愁が放たれています。この曲は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)で亡くなった彼のゴッドファーザー(名付け親)の最期と、それを支えた彼の両親の献身的な介護を目の当たりにした体験に基づいています。
セカンドシングル「I’m Not Ready for the Change」のMV公開!
看取りとは、自宅を一種の病棟に変えて、相手の切実なニーズに生活のすべてを合わせるような、極めて困難で力強い愛と友情の行為だ。でもその困難さに比して、今の経済システムでは、その行為がまったく正当に評価されていないように思う。
この曲は、「友人が友人を支えること」についての静かな賛歌であると同時に、アルバム全体に通底するテーマ──壊れていく友情や、果たされなかった約束への痛み──を浮かび上がらせます。同様のテーマは「I’m Not Ready for the Change」にも反映されています。この曲では、人生のなかで繰り返し現れる心のざわめきや不安が描かれています。デヴァニーはこう語ります。
あるとき、パーティーの写真を見つけたんだ。そこには、今では別れたカップルや、疎遠になった友人たちが写っていた。数年前の写真なのに、あのメンバーで集まるのがもう “ありえないこと” になっている。その現実が、ものすごく重くのしかかったんだ。人生のページが、こちらの理解を追い越してめくられていく感覚だったよ。
サードシングル「Under the Water」のリリックビデオを公開!
『Dance Called Memory』のレコーディングにあたり、バンドは再び友人であり『Strange Disciple』のプロデューサーでもあるニック・ミルハイザー(LCD Soundsystem、Holy Ghost!)とタッグを組みました。シンセ担当のエイダン・ノエルは、「ニックと作業すると、“期待されたこと” をする必要がないと感じられるし、“特定の音を追わなければならない” という縛りからも解放される」と語ります。ベースのアレックス・マッケイも加わり、バンドは新作に新たな音色を注入しました。
たとえば「I’m Not Ready for the Change」では切り刻んだドラムブレイクをサンプリングしてマイ・ブラッディ・ヴァレンタインの『Loveless』的な感触を加え、「In Another Life」ではパーカッション全体をシンセで変調し、2000年代初頭のエレクトロ感を醸し出しています。最終的に彼らが目指したのは、むき出しの人間性と感情を、シンセを基調とした音楽の中に織り込むことでした。
クラフトワーク的な “非人間性” の追求と、ブライアン・イーノ的な “人間らしいシンセ音楽” ──この2つの思想に僕は惹かれてきた。クラフトワークは人間性を排除しようとしたけど、イーノは “人間の心に響く音” を追求した。今回は、明らかにイーノの思想に傾いたね。人工的でない、温かくてありのままの作品にしたかったんだ。今はAIが人間の創造性を置き換えようとしている時代だからこそ、僕は人間であることにフォーカスした音楽を作りたかった。
アルバムのテーマは重く感じられるかもしれませんが、デヴァニーはこう締めくくります。
絶望ではなく、“お互いの存在を本当に見つめ合える” ような感覚をリスナーに残したい。個々の苦しみが、共感によって私たちをつなげてくれる、そんなふうに思っているんだ。