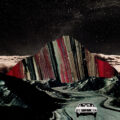2001年福岡で結成されたバンド、埋火 (うずみび) が2008年にリリースしたデビューアルバム『わたしのふね』は、時を経てもなお色褪せない “静かな衝動” を持った作品だ。日本語の繊細な歌詞と、サイケデリックかつフォーキーなアンサンブルが交錯し、聴く者の心に深く沈み込んでいくような世界を構築する。
揺れるフォークと深いベースの交歓
『わたしのふね』に収録された楽曲群は、いずれも派手な演出を排し、淡々とした中にじわりと染み込むような魅力を持っている。ギターは時にファズでざらつき、時にリリカルに旋律をなぞる。その上に、Vo/Gt の見汐麻衣の歌声がそっと重なり、透明で儚い。
特筆すべきは、須原敬三(ex.羅針盤)によるベースの存在感。このアルバムの底流を太く、確かに支える低音は、言葉では届かない感情の輪郭を浮かび上がらせる。見汐自身が「声がシャボン玉みたいにはじけるのは、須原さんのベースが大きい」と語るように、リズムと歌が互いを高め合う構造が美しい。
言葉の舟、日常と夢の狭間で漂う歌詞世界
アルバムタイトルにもなっている「ふね」というモチーフは、埋火が描く “移ろう心” や “かたちにならない想い” を象徴しているのかもしれない。「マリッジブルース」や「ひみつ」など、日常の隙間から零れ落ちる感情を繊細にすくい上げる歌詞は、聴き手の内側にある “もう一人の自分” と対話するような深みを持つ。どこか所在なげで、けれど確かにそこにある。そうした感情が丁寧に紡がれている。
統一感と余白の美学
全11曲、41分強というコンパクトな構成ながら、それぞれの曲は濃密な世界を持つ。「だから私と」から始まり「遠い散歩」で幕を閉じるまで、物語のような起伏がありながらも、全体としては静かな余韻に包まれている。アルバム全体に共通するのは “喧騒の外側にある音楽” という感覚だ。リリースから時が経ち、今聴くごとに新たな感触を見つけることができる。
『わたしのふね』は、一聴すると控えめに感じられるかもしれない。しかし、数回聴くうちに、その静けさの中にある熱、ざらつき、そしてやさしさが聴き手に無条件に忍び寄ってくる。
『わたしのふね』は、聴くたびに心の水面がゆらぎ、静かに満たされていくようなアルバムだ。